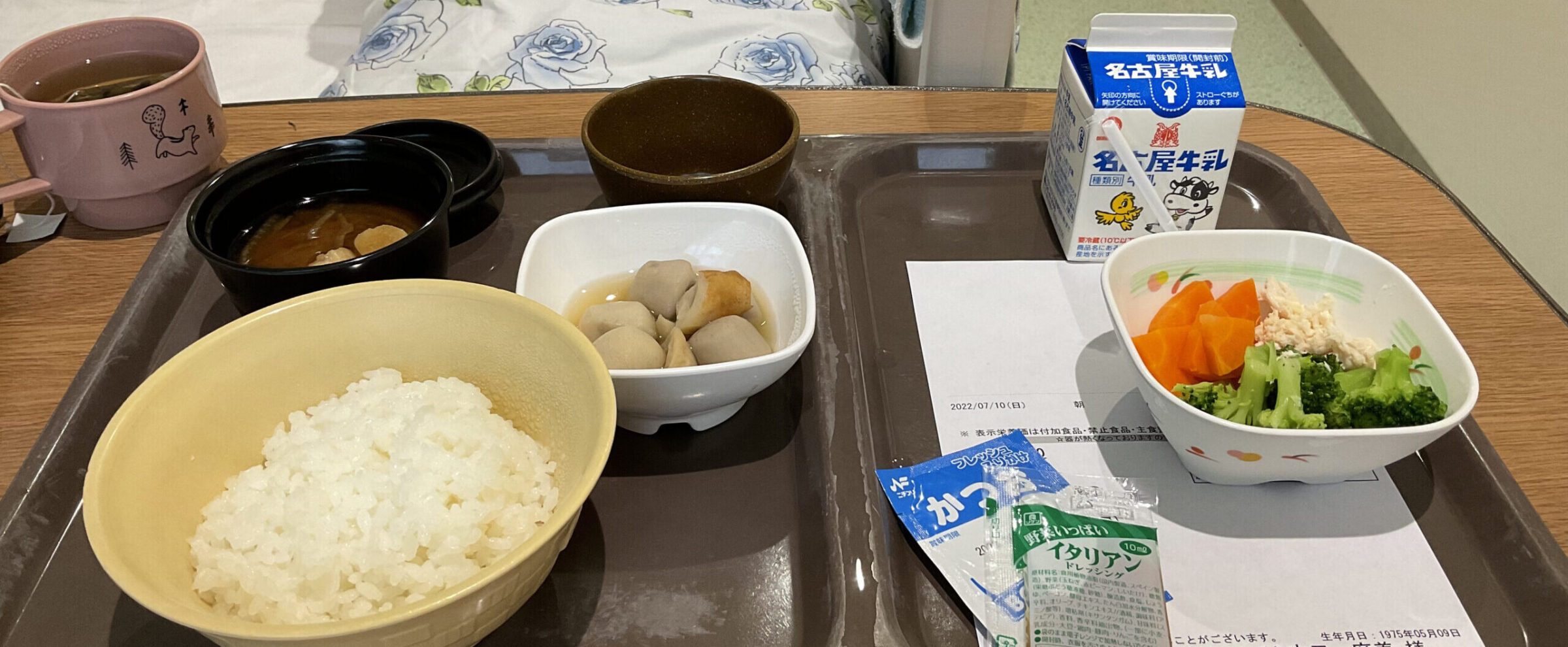茶道を習い始め、早7年が経とうとしています。
未だ上達したなぁと思う日はありませんが、今年は初釜に2回お邪魔したので、体験記を備忘録です。
犬山 有楽苑(うらくえん)での初釜
有楽苑(うらくえん)とは
ご存知の方も多いと思いますが、犬山には国宝「如庵(じょあん)」があります。
織田信長の弟である織田有楽斎が京都の建仁寺に建てた茶室を、紆余曲折を経て名古屋鉄道が犬山城の東にと移築しました。昭和11年に国宝の指定を受けた大変重要な茶道文化の遺構です。
国宝の如庵でお茶を頂く事はありませんが、日本庭園の有楽苑の中にある弘庵で受付待機、元庵で薄茶を頂いてきました。(如庵でお茶を頂ける特別な会も、過去にはあったと聞きました。)
有楽苑 初釜2023

初釜にお邪魔する度に、初釜特有のおもてなしについて勉強させて頂いております。
今回の犬山は、日本庭園有楽苑の入り口には、草履を履き替えるスペースが用意されていました。
そこで自分の草履を白い鼻緒の草履に履き替えさせられ、受付場所である弘庵へ向かいます。
※草履を脱ぐ場所は、仮設の下駄箱といった形で、ダルマストーブも置かれて暖をとる気遣いもあります。
弘庵に着くと、草履を脱いで受付を済ませます。
受付を済ませると、待合座敷には今日のお道具の入っていた箱などが並べられ、なかなか出会えない貴重なお道具なので、参加者は興味津々に文字を読んだり、歴代の宗匠の名前を確認したりします。
今回は、しだれ柳にお餅をつけた花餅というんでしょうか、赤い毛氈(もうせん)の上に、竹に花餅が桜の様にあしらわれ、少し早い春を思わせる演出がされていました。
開催主さま、この会を催される先生は本当にご苦労だと思いますし、随所に客を楽しませてくれるところが、おもてなしを受けている事に嬉しさがこみ上げるポイントです。

その素敵な座敷では、お茶席の順番を待ちます。
私が行ったこの日、なんと1日で600人分のチケットが売れていたそうで、30人同時に席に入ったとしても、1席30分位はかかるので最後はどうなってたのか心配です。
やっと呼ばれて草履をはき直し、お茶席である旧正伝院書院に歩いて移動します。
お天気に恵まれて、本当によかったと思っています。
旧正伝院書院に入ると、入り口のロッカーに荷物をつっこみ(笑)、一方通行で茶席に向かいます、が、またここでも待合があり、6畳くらいの部屋にみんなギュンギュンになって、古い建造物を見たり、掛け軸をみたり、庭をみたりして、順番を待ちました
さて、ようやくお席に、となりますが、重要なポイントである席取りが始まります。
席が決まるまでが大変です。これに一番時間がかかる事もあります。笑。
お正客(しょうきゃく)さまと呼ばれるポジションは、一番先頭に座るのですが、この役目が本当に大変で、知識のある人だったり、お話が上手な人が座らないと大変な事になります。
通常、席に入る前に掛け軸やお花、炭や道具を拝見して席に着くのですが、お茶を習ってない人もいる犬山の初釜なので、席を決めてから道具や掛け軸を拝見させていただきました。
ちょっと記憶があいまいですが、ポスターと同じ道具を使われていたので、そこは中心に見つつ、お釜や炭や炉口も見どころなので、時間の許す限り拝見させて頂きます。

お正客さまは、道具の知識もないと会話にならず、作法の順番も分からないと、声がけのタイミングも分からないとお点前が止まってしまう事もあります。書の勉強も必要かもしれません。汗。
私たちのような未熟者には遠い遠い席、そして、お点前を見える場所に座りたかったりすると、目を光らせた先生連中に囲まれたりしたら、また大変、自分が焦ってなにか間違えると、恥ずかしい塊になります。
お菓子も重箱に入ってやってくるのですが、区切れめの席になるとやる事があるし、なかなか運と度胸も必要となってきます。なんなら慣れない着物を着ているので、動きも不自然になる訳です。
この日私は自分の師事している先生一家に並んで付いて行ったので、一緒に習っている方と先生一家の並びに座るつもりが、間に他のお客さんに入られてしまい、お点前が少し見にくい席になりました。
それでも、お菓子の切れ目でもなく、なかなか安心して居られたので、良かったです。
コロナが流行して以来、初釜は中止されていました。
今年は犬山観光ホテルからホテルインディゴ犬山に変わって初となりましたし、コロナの警戒も少し溶けた久しぶりの初釜開催でした。
コロナが流行してから、和菓子にはプラスチックのカバーが着いてやってきます。
席には、誰でも手の届く間隔で除菌シートとゴミ箱が用意されていました。もちろんマスクは必須です。
着物でお茶を呼ばれるときに、使用した懐紙(かいし)やお菓子から出たごみは袖にしまうのですが、withコロナでお茶席もアップデートされていて、和菓子をカバーしていたプラスチックを回収するお盆も回ってきました。
withコロナでアップデートされた事と言えば、お茶には薄茶と濃茶があるのですが、薄茶はそれぞれの椀で飲むのですが、濃茶は何人かで同じ椀を回し飲みをするのが作法でした。
しかし、コロナ以降濃茶は各自それぞれの椀で出されるようになり、私は内心嬉しく思っています。
今までの濃茶は、3人分などとして1つの椀で出され、飲み方も2口半と決まっていて、前の人が多く飲めば、自分の分は少ないですし、前の人が遠慮していると、自分が2口半で飲むことが難しくなる、なかなかハードルの高いお茶です。そして、人が口をつけたお茶なのは言わずもがなです。
コロナ以降、美味しい濃茶を自分の分だけで飲める、これには喜びをかみしめています。笑。濃茶は薄茶よりランクの高いお茶を使うので、甘みを強く感じる、美味しいお茶が使われます。それが自分の分だけというのは、幸せの極みです。ちなみに犬山の初釜は、薄茶のみです。
話は戻り、お茶の席です。
みなさんが席に座られると、お正客さまが開催主の方へ本日はこのような席を用意してもらいありがとうございました、、云々お礼を伝えます。
開催主さまも本日は天候に恵まれ、、云々、良く来てくれましたなどとお返しの言葉を伝えます。
今回、開催主の先生がなかなか面白い発言をされたので、席は少し湧きまして、私たちも緊張から少し解放されました。
内容としては、ちょっと心配な自虐ネタでしたが、見ず知らずの人30人を前にお話しできる度胸?は、関心して、尊敬してしまいました。お茶って敷居が高いと思われている方も多いと思いますが、つっこめるポイントも多く、そのつっこまれる方も上手に返してくださる、素敵な空間です。
お菓子の提供も、有名どころが用意されるので、絶対に外れません。
美味しいお菓子が運ばれてきて、「お菓子頂戴します。」のご挨拶をして、薄茶が運ばれる前にお菓子を平らげます。
甘さを感じた後に運ばれてくる薄茶は、美味しくもあり、茶碗も練習用と違うので、見ごたえもあります。お茶を楽しんだ後は、なぜ今日の掛け軸を用意したのかなど、道具の由来など、お正客様のお尋ねの時間があります。その時に、理由、ストーリーを聞くのが私にとって更に至福の時間です。
自分が訊ねる事ができる日が来るとも思いませんが、博識の方同志のやりとりは、勉強になります。ただ、家に帰って道具の1つも思い出せない時、泣けます。。。私の記憶力、どこ行った。しょぼん。
朝起きてからの準備、犬山までの移動、お茶席までの待機等、色々考えると、あっという間にお茶席は終了します。この後、私たちはホテルインディゴ犬山に移動し、簡単なお正月料理の接待を受けます。
犬山の初釜は、表千家の同門会で担当を送っているとの事で、私が師事する先生も何度か担当をされたとの事でした。
昔はお茶席含め4000円で参加できたとの事でしたが、今年は6000円でした。(税込み)
犬山観光ホテルから外資系ホテル、インディゴ犬山に変わってから和食についてあまり良い評価はなかったみたいで、今回もホテルのシェフではなく外注でお食事の提供となったようでした。
お茶席を出て、草履を自分のものに履き替え、新しいホテルインディゴに入ると、食事会場の前には着物姿のご婦人など長蛇の列ができていました。

そうです、今日は1日で600人来るのです。お食事会場には、横並びに席が用意され、早い人から食事を済まし、順番に席が空く毎に次の人が入るシステムでした。コロナの警戒もありますので、扉は換気の為、開いています。少し並んで待ち、少し座って待ち、お食事が運ばれて、黙食に近い感じで料理を食べて、初釜が終了しました。

犬山観光ホテル時代に比べれば、綺麗でおしゃれなんですが、なんだかサラッとしすぎていて、寂しく感じられました。ホテルのスタッフも若い方が多くて、犬山という土地に見合う深みのあるホテルになっていって欲しいなと思いました。

犬山の初釜まとめ
- 参加費用は6000円(税込み)
- 薄茶とホテルインディゴ犬山でお正月料理の接待
- 犬山遊園駅から歩いて10分位(着物なので)
- 有楽苑の入り口で履き物を草履に履き替えさせられる(靴下注意)
- 成田山への初詣客が多いので、車より電車で行くのがベスト
- チケットの販売は名鉄、欲しい日が売り切れになる事もあります
- 2023年初釜のチケットは2022年10月1日~12月20日まででした
- 会主は表千家同門会愛知支部内で持ち回り
お茶だけは辞めずに続けられている不思議

お茶室って、3畳くらいしかないのを知ってますか。
どこの茶室を見ても、暗くて狭い。しかも入り口も小さい。
千利休が活躍した時代、利休は戦場でお茶をたてて、武士の武運を願い送り出してました。
戦場に出た瞬間に命を落とす可能性のある武士に、どんな気持ちでお茶をたてていたのか。
熱田神宮には、鍋よりでかい抹茶茶碗が展示してあります。
大きな茶筅も展示してあります。
その大きな茶碗で戦場に向かう武士達が同じお茶を飲んだとされています。同じ釜の飯を食った仲間ですかね、結束が深まったんでしょうか。
有楽斎は、織田信長の実の弟、体の大柄な人だったと伝えられています。
利休は小さな茶室で膝を付け合わせ、客人をもてなしていたようです。
そのもて
そのころ手珍しかった外国の茶碗や茶入れなどを使うこともおもてなしでした。自作した茶杓(ちゃしゃく)などにも利休が名(めい)をつけるのですが、それは的確で、今でも物によっては博物館で見ることができます。超名物となりますね。
利休は、豊臣秀吉に切腹を言い渡され、自害するまで全く言い訳をしなかった様です。
その頃の茶人で、才能がありながら、酷い結末を迎えた利休の弟子もいました。
利休に関して、色々な伝え方をされていますが、利休の弟子、三井寺の本覚坊という人が日記のようなものを残しており、井上靖がまとめ書いた「本覚坊遺文」という書籍があります。
本覚坊は、利休の死の謎を追いつつ、弟子として学んだ時間の中で、有楽斎の事も書いています。
有楽斎は、狭い茶室より大勢で集まれる茶室を好んだそうです。
その理由は何だったんでしょうか。
建仁寺に建てられた茶室が、名古屋鉄道のおかげで犬山という地で間近に見る事ができる。
有楽斎が如庵に込めた思いも、今の犬山の有楽苑ボランティアの方が解説してくださいました。
窓や光、狭い茶室の中の建設の工夫、聞きながら、自分が茶室に入った気持ちになって、体の大きな有楽斎にもてなされている妄想、どうでしょうか。
明日死ぬかもしれない戦場にいる訳ではないけれど、おもてなしって、ストーリーを聞くだけで優しい気持ちになれませんか。
茶室の入り口は、縦横90センチ程、武将たちは刀を預けて入らないといけませんでした。
茶室に入る前のタバコを楽しむ空間も、今と違って、趣があります。
おもてなしの方向が間違っていたとしても、自分に怒りがあっても収まっていくのを感じる事ができます。なので、茶道がとても好きです。客人を喜ばせたい気持ち、その気持ちを分かっているので、こちらも着物(正装)を着て、おもてなしに恥じない姿でお邪魔します。
何でも飽き性の私が、未だに続けていられるお茶には、こんな理由があります。